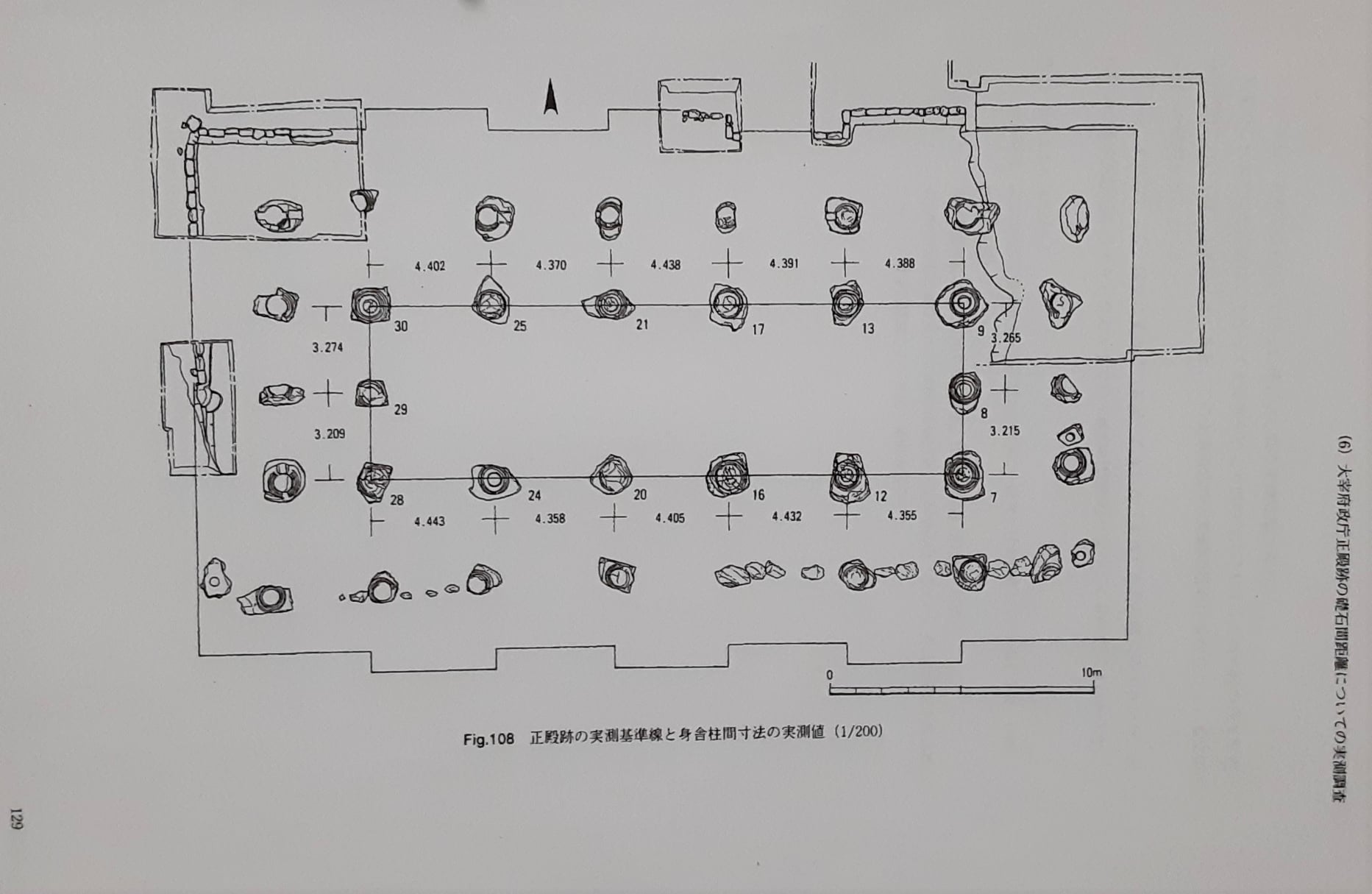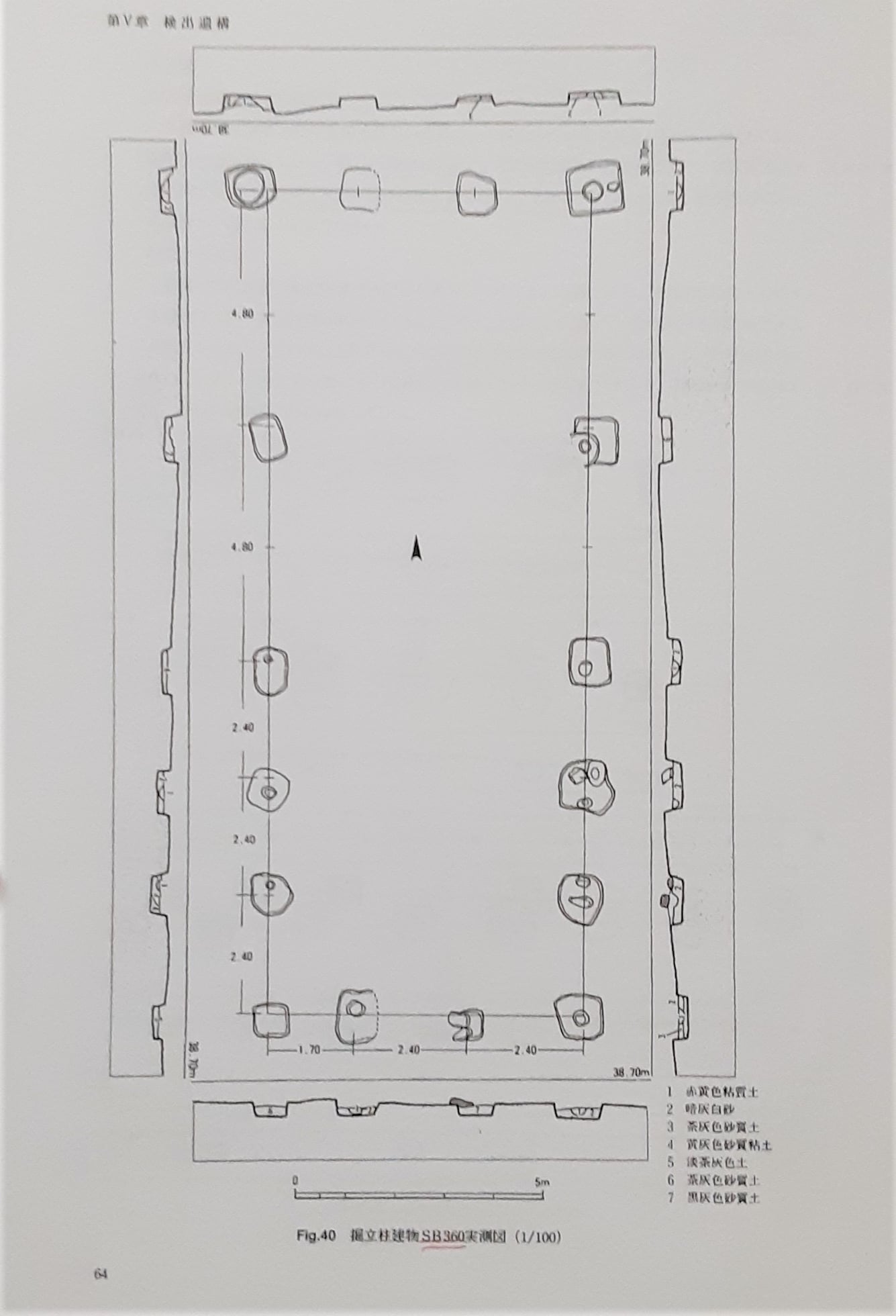『旧唐書』倭国伝「去京師一萬四千里」 (6)
いよいよ本シリーズで最も重要なテーマ、フィロロギーの視点について論じますが、その前にわたしの仮説についての理路(論理の構造と過程)を整理してみました。次の通りです。
(1) 『旧唐書』倭国伝には唐の都から倭国までの里程として「去京師一萬四千里」の記事があるが、『三国志』の短里(約77m)でも唐の長里(約560m)でも実際の距離と大きく異なり、どのように理解すべきか諸説が出されている。
(2) 「一萬四千里」は倭人伝の「萬二千余里」と唐代の長里による「二千里」が単純に加算されたものではないかとする作業仮説を発案した。
(3) その場合、加算された「二千里」は唐代の認識に基づいているので、『旧唐書』中にその「二千里」という数値が導かれた根拠があるはずである。
(4) 倭国に至る途中の国々のことが記された東夷伝に「二千里」の根拠を求めた。
(5) 高麗(高句麗)伝に次の里程記事があり、その差がちょうど二千里となる。それ以外に二千里となる数値を今のところ見いだせない。
(a) 「(高麗の都、平壌は)京師を去ること東へ五千一百里」
(b) 「(高麗の領域は)東西三千一百里」
(6) そうであれば、この差の二千里は、高麗の西端から京師(長安)までの距離と『旧唐書』編者は認識していたことになる。
(7) 高麗の西端の位置を示す次の記事が同じく高麗伝にあり、それは遼東半島の西側にある遼水(現、遼寧省遼河)付近となる。
(c) 「西北は遼水を渡り、榮州に至る」
(8) 他方、『旧唐書』編者が参考にしたであろう唐代成立の〝同時代史料〟『隋書』俀国伝の俀(倭)国への里程記事の起点は「楽浪」とされている。
(d) 「古に云う、楽浪郡の境および帯方郡を去ること一萬二千里」
(9) 『旧唐書』地理志に次の記事が見え、高麗西端の遼東に古の楽浪があったと『旧唐書』編者が認識していたことを示している。
(e) 「漢地の東は楽浪・玄菟に至り、今の高麗・渤海なり。今の遼東にあり、唐土にあらず」
(10) 以上の史料事実と考察によれば、高麗の西端(古の楽浪)から倭国までの距離を一萬二千里と『旧唐書』編者は認識していたと考えられる。
(11) そして、京師(長安)から倭国までの距離を「一萬四千里」としていることから、京師から高麗の西端までの距離を『旧唐書』編者は二千里と認識していたことになる。
わたしの仮説はこのように展開したのですが、その結果、京師(長安)から遼河(遼水)河口付近までの距離を二千里と『旧唐書』編者が認識していたということになりました。しかし、現代のわたしたちの認識(知識)では、地図上での実際の距離は直線距離でも約1,300㎞であり、これだと『旧唐書』での1里が約650mとなってしまい、約560mとされている唐の長里とは大きく異なってしまいます。
このようなとき、古田史学で重視されるのがフィロロギーという学問の方法です。すなわち、現在の常識や知識ではなく、当時の史料編者や読者の認識で史料を理解しなければならないという視点です。(つづく)