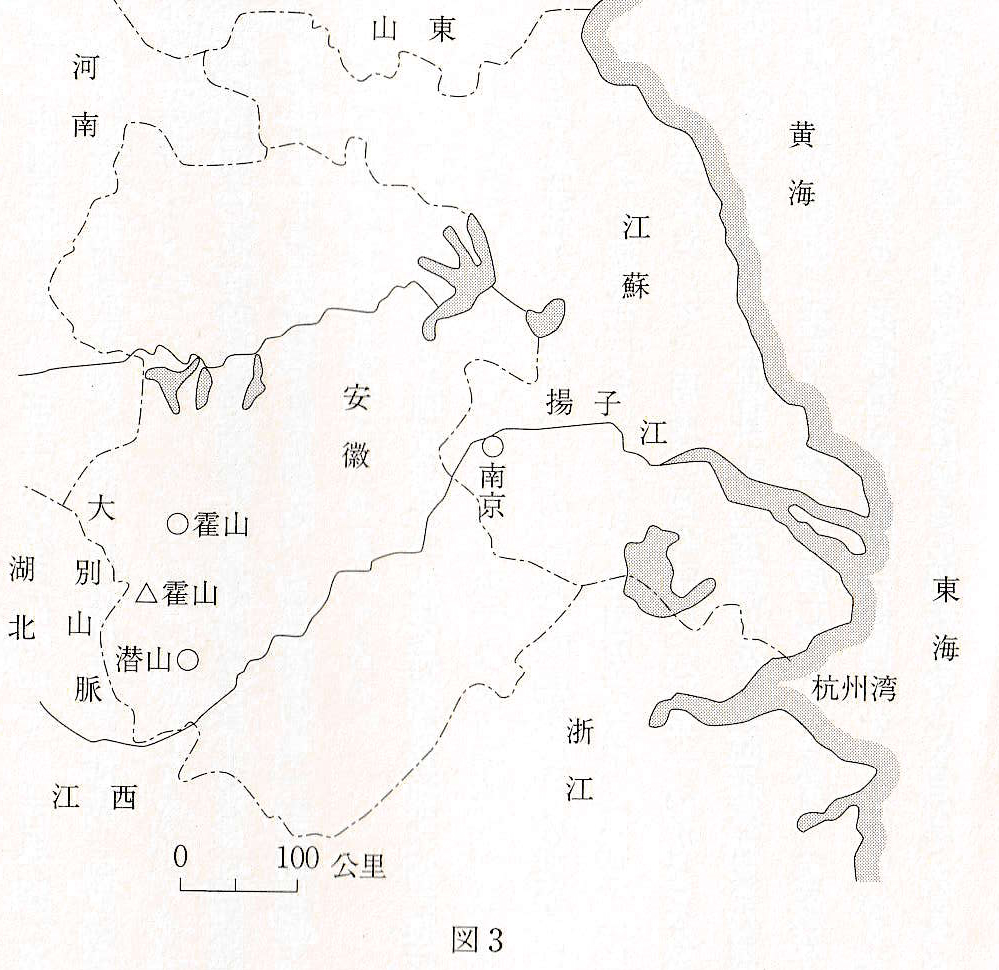倭人伝「万二千余里」のフィロロギー (8)
―フィロロギーによる論理考察―
本テーマの最後に倭人伝研究における古田先生の学問の方法について要点を解説することにします。古田史学の際だった特徴は、フィロロギーという学問の方法を文献史学に意識的に徹底的に導入したことにあります。
フィロロギーとは〝論理を愛する〟とでも言える方法論で、倭人伝研究では西晋の史官である陳寿の立場や人格なども含めて考察の対象とし、史料の一字一句の持つ意味を、著者陳寿の気持ちになって研究者が再認識するという方法論です。その場合、同じ人間として、理性に基づき論理的に記したであろうと、まずは考えます。そして、書かれている「史料事実」を「歴史事実」と見てよいのか、論理に矛盾はないのか、安定して成立している先行研究や関連諸学との関係性に問題はないのか、などを理詰めで考え抜きます。こうした姿勢を表したのが「論理の導くところへ行こう。たとえそれが何処に至ろうとも。(ソクラテス)」(岡田甫先生による)という言葉です。
具体例で説明しますと、倭人伝行路里程記事について、古田史学・フィロロギーでは次のような論理考察が進みます。その一例を示します。
❶倭国に派遣された魏使や、20年にわたり倭国に滞在したとされる張政らの報告書に基づいて、陳寿は倭国への部分里程や総里程を記載できたと考える他ない。
❷この際、総里程を陳寿自身が計算したか、または報告書に記された総里程を採用したことになる。
❸どちらの場合でも、部分里程を合計した数値を総里程としたはずである(「部分の総和は全体」は今も昔も公理(理性の鉄則)であるため)。魏使の報告書に総里程があった場合、魏使が報告した部分里程の合計と一致するかどうかを、魏使の上司や陳寿、他の官僚は確認するはずだ。
❹陳寿の『三国志』は政敵がいた中で、優れた史書であることが認められて正史として西晋の天子に献上されている。従って、政敵からの厳しいチェックを経たはずである。
❺その上で『三国志』は正史として採用されており、ときの天子や官僚、史官等が読んでも問題ないと判断されたと考えられる。中でも倭人伝は夷蛮伝の最後を飾る伝で、一層の注目をあびたと思われる。
❻更に、現存『三国志』版本には後代(五世紀)の裴松之による検証を受けており、問題ありとされた箇所には裴松之の膨大な注(裴注)が付記されている。しかし、倭人伝行路里程記事部分については、注はなく、裴松之のチェックをクリアしたと考えられる。
❼以上の考察の結果、『三国志』の記事は当時の編纂者・読者の認識を正確に表していると考えられる。従って倭人伝の記事や文字を、現代人の認識(大和朝廷一元史観)や自説(「邪馬台国」畿内説)に不都合という理由で改定したり、「信用できない」として無視してはならない。それでも、原文が間違っている、信用できないとするのであれば、そう考える方に論証責任があり、その逆ではない。
最後に古田先生の著書『九州王朝の歴史学』「部分と全体の論理 ――「穆天子伝」の再発見」の「あとがき」を転載します(注)。これからの倭人伝研究が真に学問的手続きを経たものとなることを願うばかりです。
【以下、転載】
従来の「邪馬台国」研究史上、さまざまの立論がなされてきた。そのさい、諸家必ずしも「行路里程記事」について議論せず、率爾として〝自家の邪馬台国〟を語るものも、少なしとしなかったのである。
ことに、考古学者などの場合、この記事のいかんに頓着せず、直ちに「邪馬台国」の所在を論ずる者、むしろ通例だったのである。これ、その「専門」上、止むをえぬところと見えるかもしれぬ。
しかし、精思すれば判明するように、これはことの道理に反している。なぜなら、倭人伝中に実在するのは、「行路里程記事つきの中心国(邪馬壹国、いわゆる「邪馬台国」)」であって、決して「同記事抜きの中心国」ではない。しかるに、あたかも「後者」が倭人伝中の中心国の姿であるかのように、「同記事抜き」で、ただ「邪馬台国」という国名のみ抜き出して、処理しようとするのは不当である。
もちろん、弥生時代の日本列島において、A(九州)・B(近畿)等、各地における〝中心領域〟を指摘すること、考古学者たちの任務であること、言うまでもない。
しかし、この弥生期日本列島中のいずれの地が、倭人伝内の中心国か、という比定作業にうつるさいは、必ず「行路里程記事つきの中心国」でなければならず、決して「右抜きの中心国」ではない。
すなわち、倭人伝内の中心国をとりあげるさい、肝心の「行路里程記事」を切り捨てて中心国名だけを抜き出して使用する、そのような権利は誰人にも存在しないのである。
以上のように考えてくれば、本稿のしめした帰結は、考古学・文献学・民俗学等のいずれにおいても、倭人伝内の中心国名にふれようとする限り、万人に回避しえぬテーマであることが判明しよう。それはわが国の歴史学の新たな出発点となるであろう。
【転載、おわり】
フィロロギーはドイツの古典文献学者・歴史学者アウグスト・ベーク(August Boeckh 1785~1867年)が提唱した学問で、古田先生の恩師、村岡典嗣先生(1884~1946年、東北大学)がわが国にもたらし、弟子の古田武彦先生らが継承されました。わたしたち古田学派はそれを受け継いでいます。(おわり)
(注)古田武彦「部分と全体の論理 ――「穆天子伝」の再発見」『九州王朝の歴史学 多元的世界への出発』(駸々堂、1991年)。