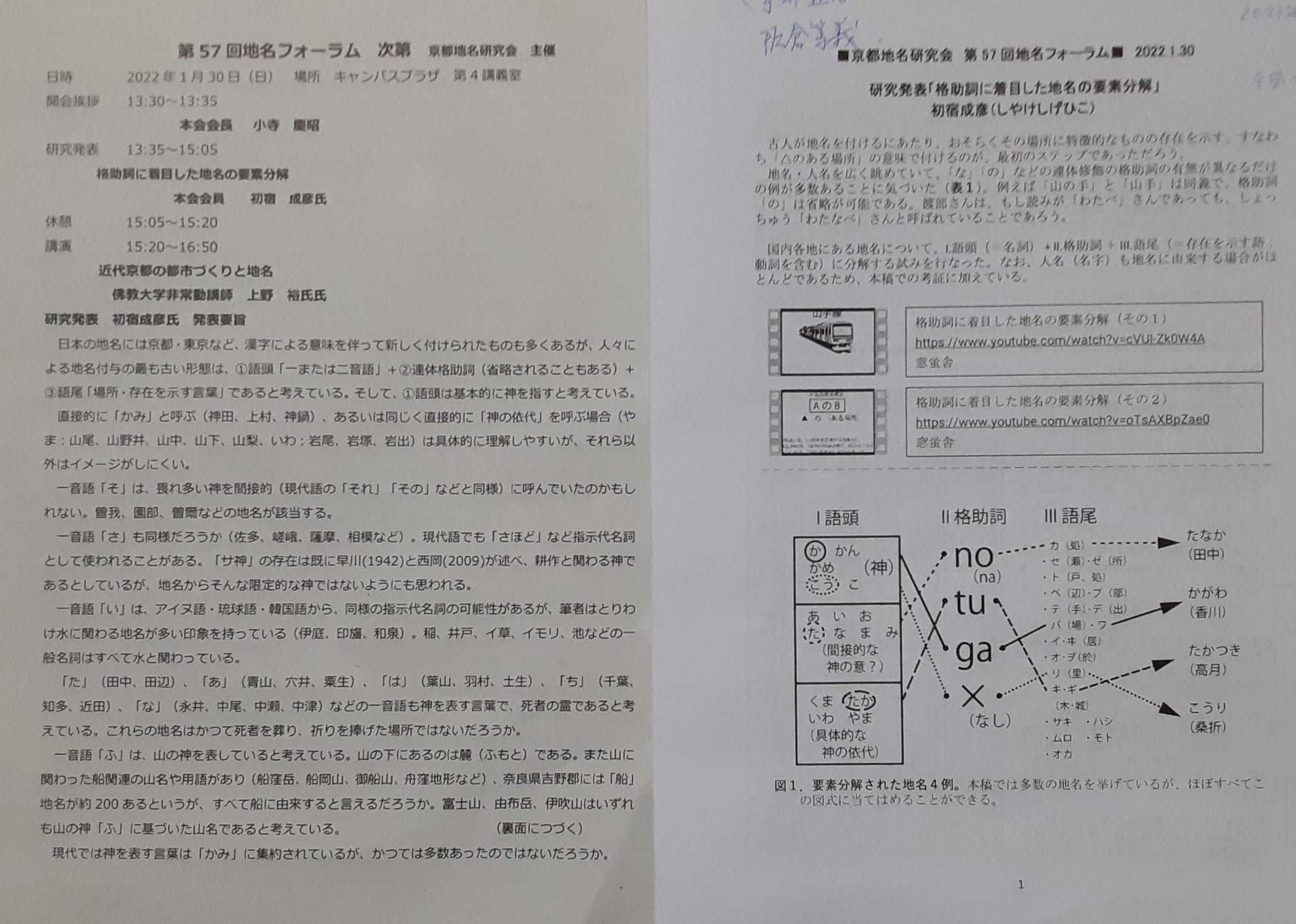『東京古田会ニュース』217号の紹介
『東京古田会ニュース』217号が届きました。拙稿「秋田孝季と橘左近の痕跡を求めて」を掲載していただきました。同稿では、『東日流外三郡誌』編者の秋田孝季と和田長三郎吉次の実在証明調査の最新情報を紹介しました。中でも和田長三郎吉次については、五所川原市飯詰の和田家菩提寺、長円寺にある墓石の戒名・年次(文政十二年・一八二九年建立。注①)と過去帳に記された喪主の名前「和田長三郎」「和田権七」などから、その実在は確実となりました。
秋田孝季については今も調査中ですが、『東日流外三群誌』に「秋田土崎住 秋田孝季」と記される例が多く、孝季が秋田土崎(今の秋田市土崎)で『東日流外三群誌』を著述したことがわかっていました。そして太田斉二郎さんからは、秋田市土崎に橘姓が多いことが報告されています(注②)。全国的に見れば、秋田県や秋田市に橘姓はそれほど多くはないのですが、秋田市内の橘姓の七割が土崎に集中していていることを秋田孝季実在の傍証として紹介しました。
当号に掲載された安彦克己さん(東京古田会・会長)の「『和田家文書』備忘録7 遠野の古称は十戸」を興味深く拝読しました。その主テーマは和田家文書を史料根拠として、岩手県遠野市の名前の由来が「十戸」にあったとするもので、当初、わたしは「十戸(じゅっこ)」と「遠野」とどのような関係があるのか理解できませんでした。しかしそれはわたしの思い違いであり、「十戸(とおのへ)」と訓む論稿だったのでした。そうであれば「十戸(とおのへ)」の「へ」が何らかの事情で消え、「とおの」という訓みで地名が遺り、後世になって「遠野」の字が当てられたとの理解が可能です。
念のため、「遠野」の由来をWEBで調べたところ、朝日新聞(2010年10月6日、注③)の記事に次の説が示されていました。
〝「日本後紀」に「遠閉伊(とおのへい)」が登場することに注目。閉伊の拠点であった宮古地方から遠いところという意味で、「後年、そこから閉伊が抜け落ちた」〟
この「遠閉伊(とおのへい)」説は『日本後紀』という史料根拠に基づいており有力と思いますが、わたしは地名を漢字2文字で表すという公の慣行により、「へ」という地名に「閉伊」という漢字が当てられたように思います。そうであれば、「遠閉伊(とおのへい)」の古称は「十戸(とおのへ)」であり、岩手県と青森県に分布する「一戸(いちのへ)」~「九戸(くのへ)」と同類地名としての「十戸(とおのへ)」であり、後世になって「遠野」の字が当てられたものと思います。もしこの解釈が妥当であれば、和田家文書の伝承力は侮れないと思いました。
(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」三〇三六話(2023/06/09)〝実在した「東日流外三郡誌」編者 ―和田家墓石と長円寺過去帳の証言―〟
墓石には次の文字が見える。()内は古賀注。
〔表面〕
「慈清妙雲信女 安永五申年十月(以下不明)
智昌良恵信士 文化十酉年(以下不明)
安昌妙穏信女 文化十四丑年(以下不明)
壽山清量居士 (没年記載なし)」
〔裏面〕
「文政丑五月建(一字不明、「之」か)和田氏」
壽山清量居士(和田吉次と思われる)が存命の文政十二年(一八二九)に建立した墓碑であろう。
②太田斉二郎「孝季眩映〈古代橘姓の巻〉」『古田史学会報』二四号、一九九八年。
古賀達也「洛中洛外日記」三九二話(2012/03/05)〝秋田土崎の橘氏〟
③朝日新聞(2010年10月6日)の記事
発刊100年を迎えた「遠野物語」。その中で柳田国男は、「遠野」という地名の由来をアイヌ語に求めた。しかし、そこに異議をとなえる研究者もいる。
「遠野物語」で柳田は、トーは「湖や沼」。ヌップが「丘」。太古、遠野郷は湖だった。その水が流れ出て、今の盆地が現れたという神話と結びつけて「湖のある丘」と解釈した。多くの遠野市民もそう思っている。
「私はそうは思いません。遠野は和語だと思います」
5月に遠野市で行われた全国地名研究者大会(日本地名研究所主催)で、アイヌ語学者の村崎恭子・元横浜国大教授(73)はアイヌ語説を否定した。
アイヌ語の地名かどうかを検証するには、アイヌ語地名が原形に近い形で残っている北海道を手本にする。
アイヌ語で「サ」は「乾く」で、「ピ」は「小石」、「ナイ」は「川」だ。そういう状態の場所は「サピナイ」と呼ばれる。遠野郷にある「佐比内」も、かつてはそういう地形だったと思われる。
猿ケ石(サルガイシ)は「ヨシ原の上・にある・もの」で、附馬牛(ツキモウシ)は「小山・ある・所」。北海道の似た地形の場所には、似た地名が残っている。
しかし、遠野という地名は北海道にない。湖や沼や丘など、似た地形はたくさんあるにもかかわらず。
遠野と呼ばれ出した時期からも疑問を膨らませる。文献によると、遠野と呼ばれるようになったのは、中央集権化が進んだ古代。猿ケ石川などが、そうアイヌ語地名で呼ばれ出したはるか後の時代なのだ。もしアイヌ語だとすれば、なぜ遠野だけが遅れて名付けられたのか。その理由がわからない、と言うわけだ。
こう説明したあとで「遠野というのは、中心地から遠いところ、という意味で倭人(わじん)がつけたのではないかと思います」と自説を述べた。
遠野の語源に関しては「東方の野」からきた説や、たわんだ地形の盆地である「撓野(たわの)」の変化、など諸説ある。日本地名研究所の谷川健一所長(89)は、村崎説を支持した上で、平安時代に編まれた日本の正史の一つ「日本後紀」に「遠閉伊(とおのへい)」が登場することに注目。閉伊の拠点であった宮古地方から遠いところという意味で、「後年、そこから閉伊が抜け落ちた」とみている。(木瀬公二)