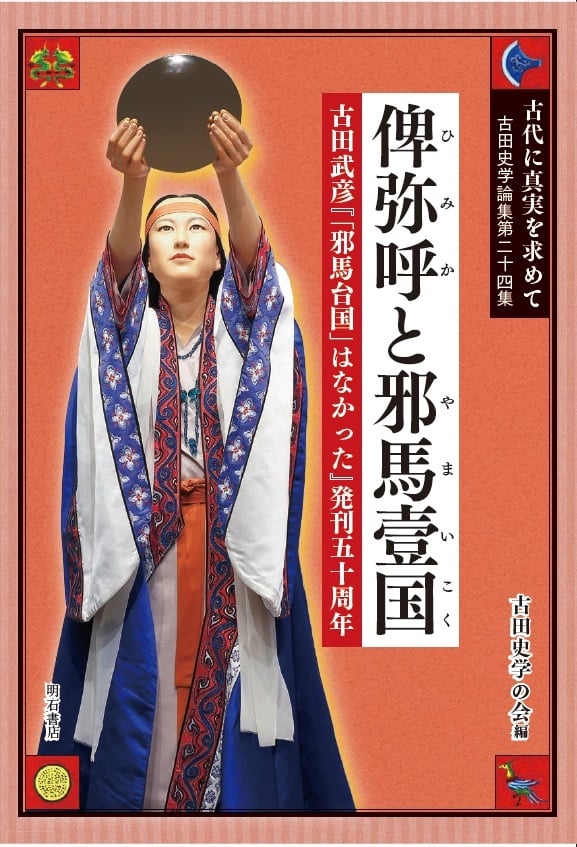飛鳥「京」と出土木簡の齟齬(5)
飛鳥木簡を調査していて気になったことがありました。以前は飛鳥出土の宮跡のことを、『日本書紀』に見える各天皇の宮殿名と対応させるように、「伝飛鳥板蓋宮跡」とか「後飛鳥岡本宮跡」「飛鳥浄御原宮跡」などと呼ばれていたのですが、いつの頃からか「飛鳥宮跡」「飛鳥京跡」と呼ばれるようにもなりました。当地が〝飛鳥「京」〟といえるほどの大規模都城の地とは思えませんので、なぜこのような名称が定着したのか疑問に思っていました。
古代史学の〝常識〟では、「京」と呼べるのは条坊都市を持つ大規模な平安京・平城京・藤原京、そして近年の発掘調査で条坊の存在が確実となった難波京くらいです。それと条坊都市を有する九州王朝の首都「太宰府(倭京)」(注①)も含まれるでしょう。そこで、飛鳥京命名についての背景や根拠を調べたところ、『ウィキペディア』の「飛鳥京跡」の項に次の解説がありました。
【以下、転載】
飛鳥宮跡の発掘調査
発掘調査は1959年(昭和34年)から始まった。発掘調査が進んでいる区域では、時期の異なる遺構が重なって存在することがわかっており、大まかにはⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期の3期に分類される。各期の時代順序と『日本書紀』などの文献史料の記述を照らし合わせてそれぞれ、
・Ⅰ期が飛鳥岡本宮(630~636年)
・Ⅱ期が飛鳥板蓋宮(643~645、655年)
・Ⅲ期が後飛鳥岡本宮(656~660年)、飛鳥浄御原宮(672~694年)
の遺構であると考えられており、Ⅲ期の後飛鳥岡本宮・飛鳥浄御原宮については出土した遺物の年代考察からかなり有力視されている。発掘調査で構造がもっともよく判明しているのは、飛鳥浄御原宮である。
地元では当地を皇極天皇の飛鳥板蓋宮の跡地と伝承してきたため、発掘調査開始当初に検出された遺構については「伝飛鳥板蓋宮跡」の名称で国の史跡に指定された。しかし、上述のようにこの遺跡には異なる時期の宮殿遺構が重複して存在していることが判明し、2016年10月3日付けで史跡の指定範囲を追加の上、指定名称を「伝飛鳥板蓋宮跡」から「飛鳥宮跡」に変更した(平成28年10月3日文部科学省告示第144号)。
【転載おわり】
同じく「飛鳥京」の項では次のように説明されています。
【以下、転載】
飛鳥京(あすかきょう、あすかのみやこ)は、古代の大和国高市郡飛鳥、現在の奈良県高市郡明日香村一帯にあったと想定される天皇(大王)の宮やその関連施設の遺跡群の総称、およびその区域の通称。藤原京以降のいわゆる条坊制にならう都市ではなく、戦前の歴史学者喜田貞吉による造語とされる。
概要
主に飛鳥時代を中心に、この地域に多くの天皇(大王)の宮が置かれ、関連施設遺跡も周囲に発見されていることから、日本で中国の条坊制の宮都にならって後世に飛鳥京と呼ばれている。飛鳥古京(あすかこきょう)や「倭京」、「古京」などの表記(『日本書紀』)もみられる。君主の宮が存在していたことから当時の倭国の首都としての機能もあったと考えられる。
しかし、これまでの発掘調査などでは藤原京以降でみられるような宮殿の周囲の臣民の住居や施設などが見つかっておらず、全体像を明らかするような考古学的成果はあがっていない。また遺跡の集まる範囲は地政的に「飛鳥京」とよべるほどの規模を持たず実態は不明確であり、歴史学や考古学の文脈での「飛鳥京」は学術的でない。しかし、現在では好事家や観光業などで広く使われ飛鳥周辺地域を指す一般名称の一つとしてよく知られる。(後略)
【転載おわり】
上記の解説によれば、従来は「伝飛鳥板蓋宮跡」と呼ばれていた遺跡が複数の宮の重層遺跡であることが判明したため、総称して「飛鳥宮跡」とされたわけで、この変更は妥当なものと思います。
しかし、〝これまでの発掘調査などでは藤原京以降でみられるような宮殿の周囲の臣民の住居や施設などが見つかっておらず、全体像を明らかするような考古学的成果はあがっていない。また遺跡の集まる範囲は地政的に「飛鳥京」とよべるほどの規模を持たず実態は不明確であり、歴史学や考古学の文脈での「飛鳥京」は学術的でない。〟としながら、〝現在では好事家や観光業などで広く使われ飛鳥周辺地域を指す一般名称の一つ〟として「飛鳥京」の名称が採用されているとのことです。
〝好事家や観光業〟が趣味やビジネスで使用するのは理解するとしても、橿原考古学研究所編集発行の書籍(注②)などに遺跡名称として「飛鳥京苑地遺構」が使われていますし、発掘調査報告書にも「飛鳥京跡」と記されています。その規模からすれば、「飛鳥京」と呼ぶのはいかがなものかと違和感を感じてきたのですが、「飛鳥京」の名称が不適切であることを、多元史観により学問的に論証したのが服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の秀逸な論文「古代の都城 ―『宮域』に官僚約八〇〇〇人―」(注③)です。
『古代に真実を求めて』21集に掲載された同論文は七頁の小論ですが、それは二十世紀最大の科学的発見といわれるDNAの二重螺旋構造を明らかにした、ワトソンとクリックによるわずか二頁(実質的には一頁)の論文(注④)を彷彿とさせます(彼らはその論文でノーベル医学・生理学賞を受賞)。この服部論文は次のシンプルで頑強な論理構造により成立しています。
(1)律令政治には官僚が業務を行う官衙と、官僚とその家族が生活する住居、この二つが必須である。
(2)『養老律令』では全国統治を行う中央官僚(宮域勤務の官僚)の人数が規定されており、その合計は約八千人である。
(3)それら中央官僚の職場と住居スペースを持つ七~八世紀の巨大都市は、前期難波宮(京)、藤原宮(京)、平城宮(京)、平安宮(京)である(いずれも条坊都市)。※後に太宰府条坊都市が追加される。
(4)飛鳥にはそのような大規模都域はなく、全国統治が可能な王都とはできない。すなわち、「飛鳥京」という名称は不適切である。
このように根拠や論理がシンプル(単純平明)でロバスト(頑強)なため、反証が困難です。この論理は通説の「飛鳥京」にとどまらず、古田学派研究者から提起された諸仮説の是非をも明らかにします。これが現在の多元史観・古田史学の論理水準ですから、律令制時代における九州王朝の都域に関する仮説を提起する場合は、この服部論文のハードルをまず超えなければなりません。(つづく)
(注)
①九州王朝の首都「太宰府(倭京)」については、『発見された倭京 ―太宰府都城と官道』(古田史学の会編、明石書店、2018年)の収録論文を参照されたい。
②『飛鳥宮跡出土木簡』橿原考古学研究所編、令和元年(2019)、吉川弘文館。
③服部静尚「古代の都城 ―『宮域』に官僚約八〇〇〇人―」『発見された倭京―太宰府都城と官道』(『古代に真実を求めて』21集)古田史学の会編、明石書店、2018年。初出は『古田史学会報』136号、2016年10月。
④〝Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid〟Nature volume 171,pages737–738(1953), J.D.WATSON & F.H.C.CRICK