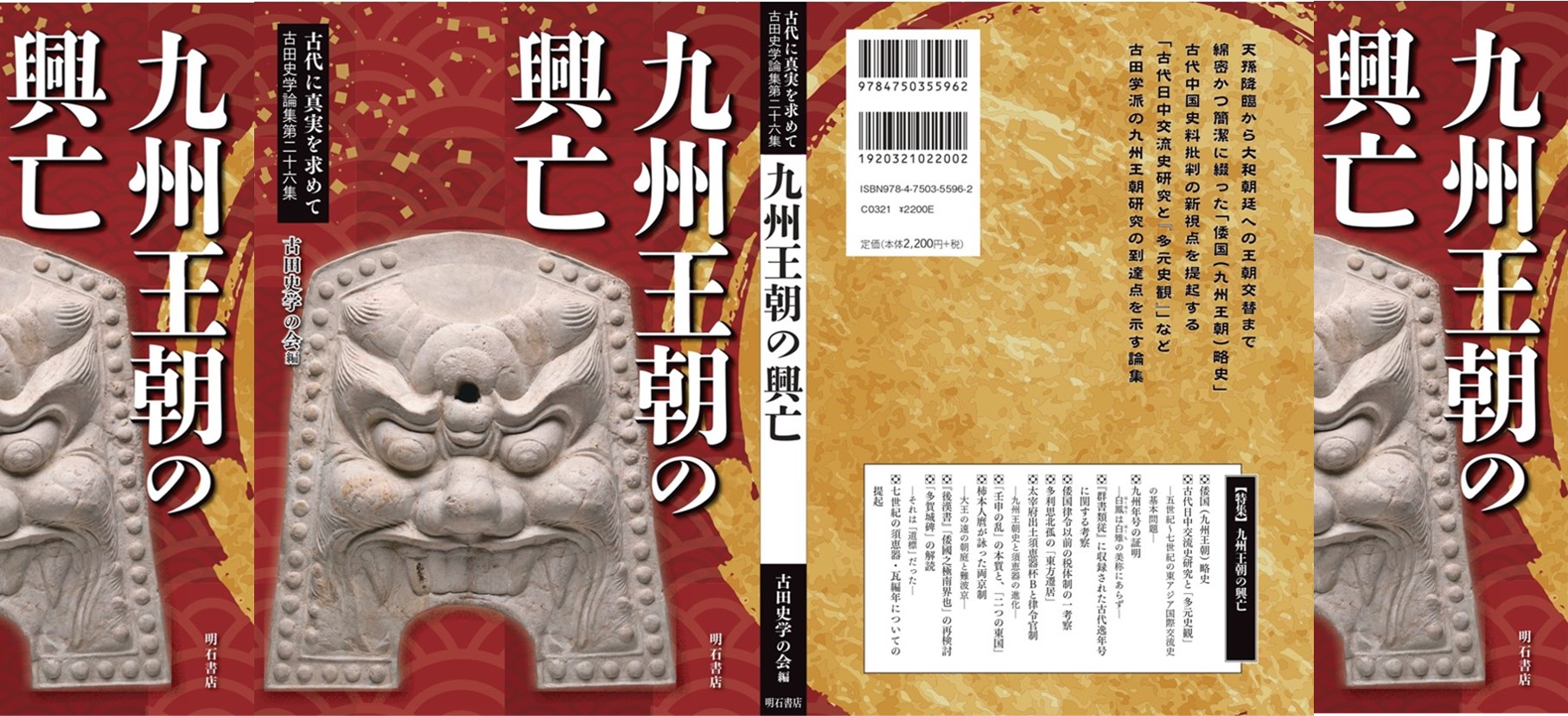吉野ヶ里出土石棺、被葬者の行方 (1)
吉野ヶ里遺跡の〝謎のエリア〟から出土した石棺からは残念ながら副葬品や被葬者は検出されませんでした。「洛中洛外日記」(注①)で「吉野ヶ里の石棺蓋の「×」印と銅鐸圏(出雲)での「×」印にどのような関係があるのか、古代日本思想史上の課題でもあり、石棺内の調査を興味深く見守っています。吉野ヶ里の有力者に相応しい金属器の出土が期待されます。」と書いていたわたしも、〝やはり出なかったのか〟とがっかりしました。というのも、石棺の蓋を開けてから、「副葬品はなかった」という報道まで間が開きすぎていたからです。
吉野ヶ里遺跡の最高所からの出土石棺ですから、当然、発掘担当者たちは一流の機材と準備をもって事に当たっていたはずです。なぜなら、石棺の蓋を開けた時点で金属探知機による副葬品の位置確認を行い、薄皮を剥ぐように慎重に発掘しなければならないからです。そうした事前準備をしていたのなら、その時点で鏡や剣など金属器の反応がないことがわかります。わたしたちにはうかがい知れない特段の事情があったのかもしれませんが、世間やマスコミの注目を維持するために、あえて発表を遅らせたのではないかとさえ邪推したくなります。もし、金属探知機を使用できないほど発掘調査の予算が少ないのであれば、当地の考古学者や行政の担当者に同情します。
ちなみに最先端機材を使用した事例として、福岡県古賀市の船原古墳発掘調査があります。それは下記のような調査方法でした(注②)。
(1) 遺構から遺物が発見されたら、まず遺構のほぼ真上からプロのカメラマンによる大型立体撮影機材で詳細な撮影を実施。
(2) 次いで、遺物を土ごと遺構から取り上げ、そのままCTスキャナーで立体断面撮影を行う。この(1)と(2)で得られたデジタルデータにより遺構・遺物の立体画像を作製する。
(3) そうして得られた遺物の立体構造を3Dプリンターで復元する。そうすることにより、遺物に土がついたままでも精巧なレプリカが作製でき、マスコミなどにリアルタイムで発表することが可能。
(4) 遺物の3Dプリンターによる復元と同時並行で、遺物に付着した土を除去し、その土に混じっている有機物(馬具に使用された革や繊維)の成分分析を行う。
こうした作業により、船原古墳群出土の馬具や装飾品が見事に復元され、遺構全体の状況が精緻なデジタルデータとして保存されました。日本の発掘調査技術はここまで進んでいるのです。(つづく)
(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」3035話(2023/06/08)〝吉野ヶ里出土石棺墓が示唆すること (2) ―蓋裏面に刻まれた「×」印―〟
②同「洛中洛外日記」2063話(2020/01/12)〝「九州古代史の会」新春例会・新年会に参加〟