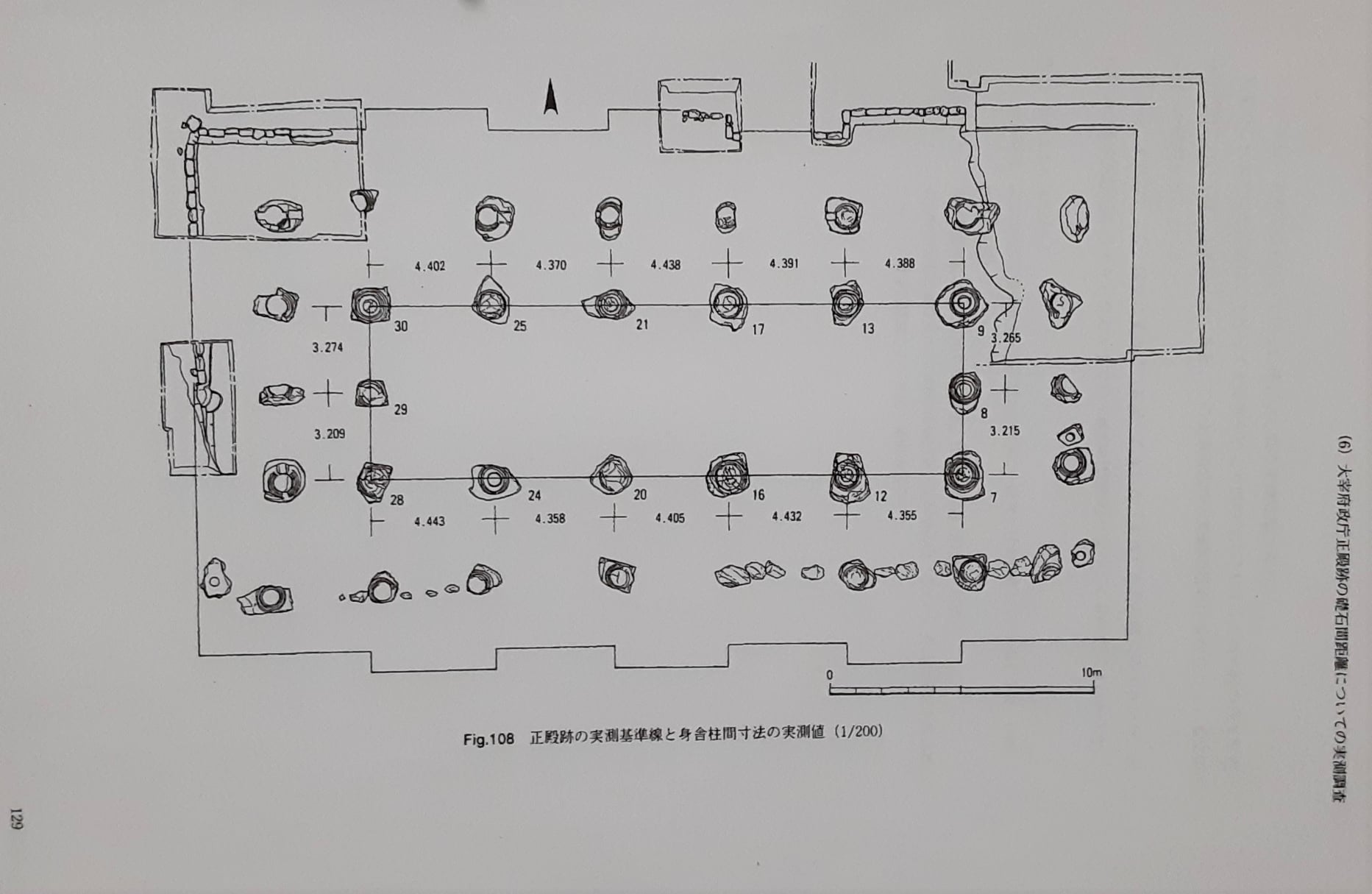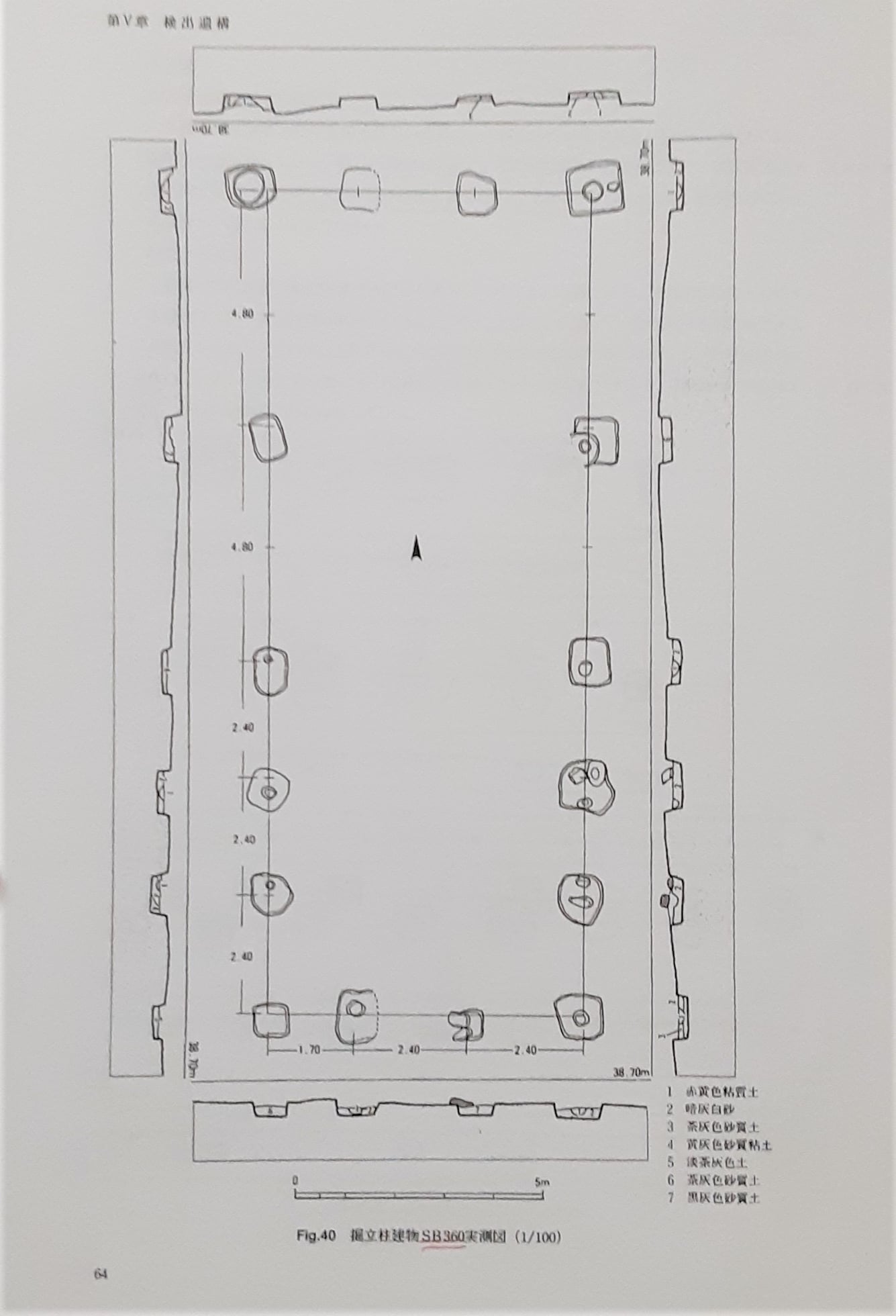『旧唐書』倭国伝「去京師一萬四千里」 (4)
『旧唐書』倭国伝には「去京師一萬四千里」とあり、『三国志』の短里(1里約77m)表記「萬二千余里」に唐代の長里(1里約560m)による二千里が単純に足されているのではないかと考え(作業仮説)、この「二千里」が『旧唐書』の中にあるはずと精査を続けました。そして、「萬二千里」部分は唐の直前の『隋書』の次の記事に依っていると推測しました。『旧唐書』編者にとって、唐代に成立した『隋書』が最も時代が近い〝同時代史料〟であり、最有力情報として参考にするはずと考えたからです。
「古に云う、楽浪郡の境および帯方郡を去ること一萬二千里」『隋書』俀国伝(注①)
この記事には、楽浪郡から俀(倭)国までの距離を「一萬二千里」としていますので、『旧唐書』編者は京師(長安)から楽浪郡までの距離を二千里と認識していたことになります。そこで、わたしは高麗(高句麗)伝(注②)の次の里程記事に着目しました。
(1) 「京師を去ること東へ五千一百里。」
(2) 「東西三千一百里、南北二千里。」
(1)は唐の京師(長安)から高句麗の都(平壌)までの距離、(2)は高句麗の領域の東西と南北の距離です。もし、平壌が高句麗の東端付近に位置していたとすれば、5,100里-3,100里=2,000里となり、この二千里が高句麗の西端付近から京師(長安)までの距離であり、わたしの作業仮説の二千里と一致します。それでは高句麗の西端はどこでしょうか。これも『旧唐書』高麗伝にヒントがありました。次の記事です。
(3) 「西北は遼水を渡り、榮州に至る。」
(4) 「儀鳳中(676~679年)、高宗は高蔵(高句麗王)に開府儀同三司、遼東都督を授け、朝鮮王に封ず。」
(3)の記事によれば高句麗の西端は遼水(注③)であり、そこを渡ると唐の榮州に至るとあります。(4)の記事では高句麗王が唐から遼東都督に任命されており、高句麗の領域が遼水の東側の遼東であることがわかります。ですから、唐代の高句麗の領域は遼東半島を含み東西に広がっていたことがわかります。
以上の史料事実に基づく考察により、追加された二千里と遼水の西岸付近から京師(長安)までの距離二千里とが一致対応するのですが、この理解を支持する記事が『旧唐書』地理志(注④)にありました。(つづく)
(注)
①岩波文庫『魏志倭人伝 他三篇』1988年版。
②『旧唐書』十六「伝十」中華書局、1987年版。
③中国遼寧省を流れる遼河。
④『旧唐書』五「志三」中華書局、1987年版。