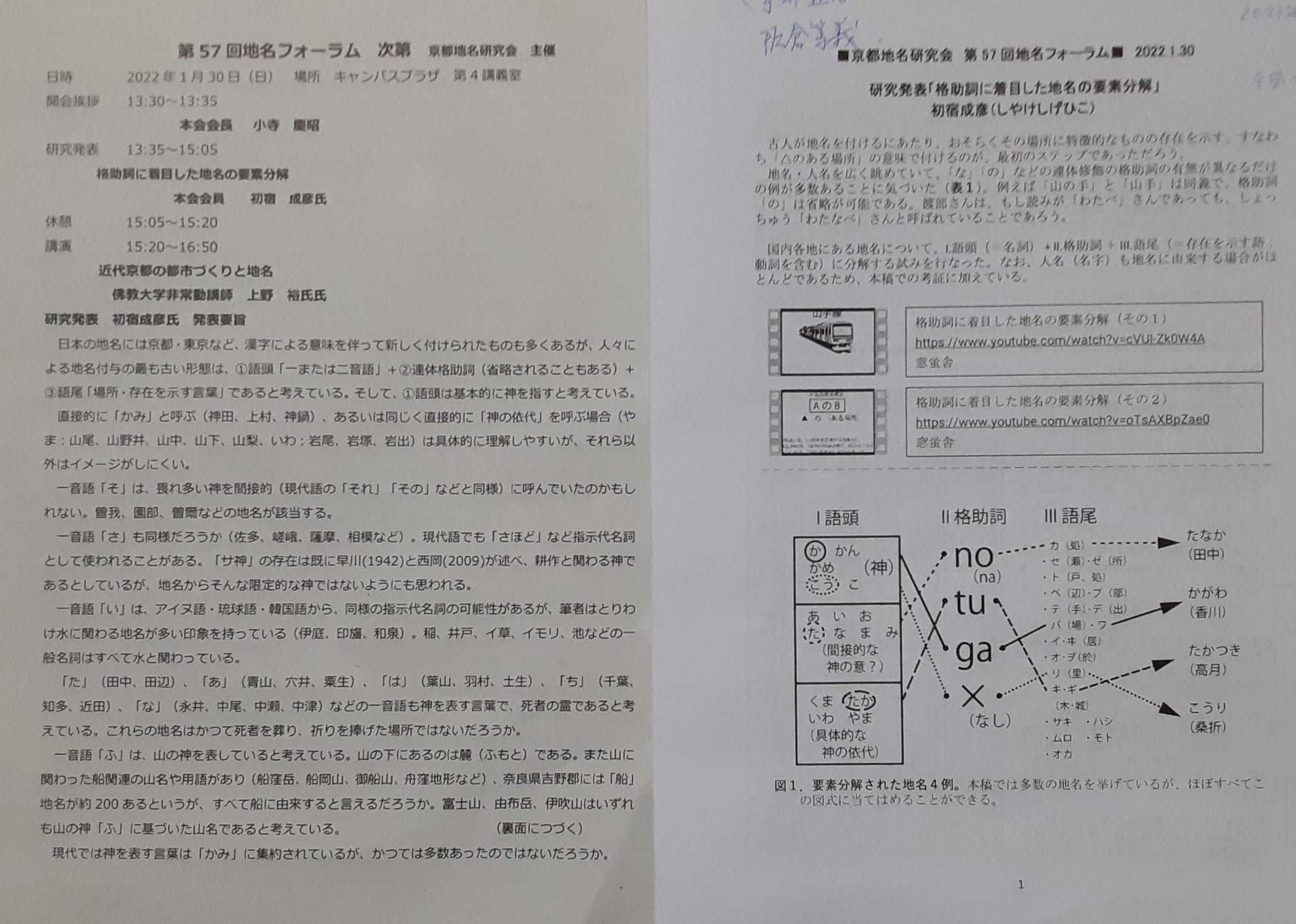古田先生の土器編年試案(セリエーション) (2)
太宰府関連遺構の全体的な編年を論じた山村信榮さんの「大宰府成立再論 ―政庁Ⅰ期における大宰府の成立―」(注①)にセリエーションという考古学の専門用語が用いられており、とても興味深い内容でした。出土土器のセリエーションという現象の比較による詳細な太宰府遺構の相対編年がなされており、その説得力を高める工夫がなされています。この山村論文では従来の編年について次のように指摘しています。
「大宰府の成立を概観する際に重要な時間軸についても解決すべき課題がある。九州における大宰府成立期に係わる考古学的な時間軸は、遺跡から出土する頻度の高い須恵器が用いられてきた。(中略)しかし、型式と期の設定を同一化し、設定した土器型式を、重箱を重ねる方式で時間軸をたてる方式には問題点があり、研究史や新たな編年案についてかつて考察したことがある。また、実年代に関わる諸問題についても指摘した。」199頁
こうした従来の相対編年方法に替えて、次のようなセリエーションの概念を導入した編年方法を明示しています。
「本稿においては九州編年における『期』として括られた遺物の一群から一つの典型的な型式を抽出し、型式間には時間の流れに従った量的増減がありながらの共伴を認め、新しい型式の出現をもって期を区切る考え方で時間軸を立てる。」200頁
そして、六~七世紀の須恵器杯H・G・Bのセリエーション(共伴状況)とその時間帯(フェイズ)を具体的に説明され、各遺構の編年を設定しています。同時にこの編年作業の難しさや限定条件についても触れています。
「(前略)一つの遺構が存在した厳密な時期を知るためには埋没した環境が知られることや、一定量の同器種複数系統の土器が出土する必要がある。現実的には本論で取り扱う官衙や古代山城の特定の一つの遺構や層から多量の土器が出土するのは稀で、少量の土器が示す時期には不確実性がある。しかし、同じ遺跡が継続して使用され、土壌の堆積や遺構の切りあいが繰り返される場合、少量の土器の出土であっても一定の時間的変遷の傾向は遺物群の前後関係から見て取れる場合が少なくない。遺構が巨大である場合は各地点で出土した少量の遺物が同一性を示すのであれば、一定の幅で遺構の存在した時期を知ることはできる。」200頁
山村さんはこのように土器のセリエーションによる遺構・層位の存在時期の幅(フェイズ)の判断の可能性について述べられており、いずれも重要な視点が含まれています。具体的には次の視点です。
(1) 少量の土器が示す時期には不確実性がある(注②)。
(2) 同じ遺跡が継続して使用され、土壌の堆積や遺構の切りあいが繰り返される場合、少量の土器の出土でも一定の時間的変遷の傾向は見て取れる場合が少なくない。
(3) 遺構が巨大である場合は各地点で出土した少量の遺物が同一性を示すのであれば、一定の幅で遺構の時期を知ることはできる。
(2)(3)の視点は、巨大遺構である大野城や水城の編年に活かされており、山村さんは出土須恵器セリエーションに基づいて、両遺構の造営時期などについて、「現状では大野城の築造開始期は『日本書紀』の記述に沿う形で理解しておく。ともあれ、出土した須恵器の土器相が水城と整合的であることを指摘しておきたい。」(203頁)としています。すなわち、両遺構の須恵器セリエーションによる相対編年と暦年とのリンクに『日本書紀』の記事(注③)が採用されていることから、大野城と水城の築造開始時期を七世紀第3四半期と〝現状では理解〟されているようです。
ちなみに、わたしは水城の完成時期を考古学エビデンスによれば七世紀中葉頃(『日本書紀』天智三年(664)水城築造記事の年代を含む。注④)、大野城はその規模の巨大さから完成は七世紀中葉(注⑤)で、築造開始は七世紀前半まで遡ると考えた方がよいと思っています。(つづく)
(注)
①山村信榮「大宰府成立再論 ―政庁Ⅰ期における大宰府の成立―」『大宰府の研究』高志書院、2018年。
②服部静尚「孝徳・斉明・天智期の飛鳥における考古学的空白」、古田史学の会・関西例会、2022年2月。同発表の質疑応答で、セリエーションによる相対編年を行う際の、母集団として必要な出土土器サンプル数についての筆者からの質問に対して、25点との返答がなされた。同研究は古田学派による初めての本格的な須恵器セリエーションの採用であり、注目される。
③『日本書紀』によれば水城の築造記事が天智三年(664)条、大野城の築城記事が天智四年(665)八月条見える。
④古賀達也『洛中洛外日記』2620話(2021/11/24)〝水城築造年代の考古学エビデンス(3)〟において、次のように述べた。同要旨を転載する。
〝水城築造年代のエビデンスとできるのは、堤体内から出土した土器です。堤体内からの出土土器は少数ですが、水城の基底部に埋設した木樋の抜き取り跡から須恵器杯Gが出土しています。他方、水城の上や周囲から出土した主流須恵器が杯Bであることを併せ考えると、水城の築造年代は杯Gが発生した7世紀中葉以降かつ杯B発生よりも前ということができます。具体的年代を推定すれば640~660年頃となり、「7世紀中葉頃」という表現が良い。〟
⑤大野城大宰府口城門から出土したコウヤマキ柱根最外層の年輪年代測定が648年とされており、大野城築造が650年頃まで遡る可能性がある。
【写真】大宰府政庁出土土器編年図(参考図です)