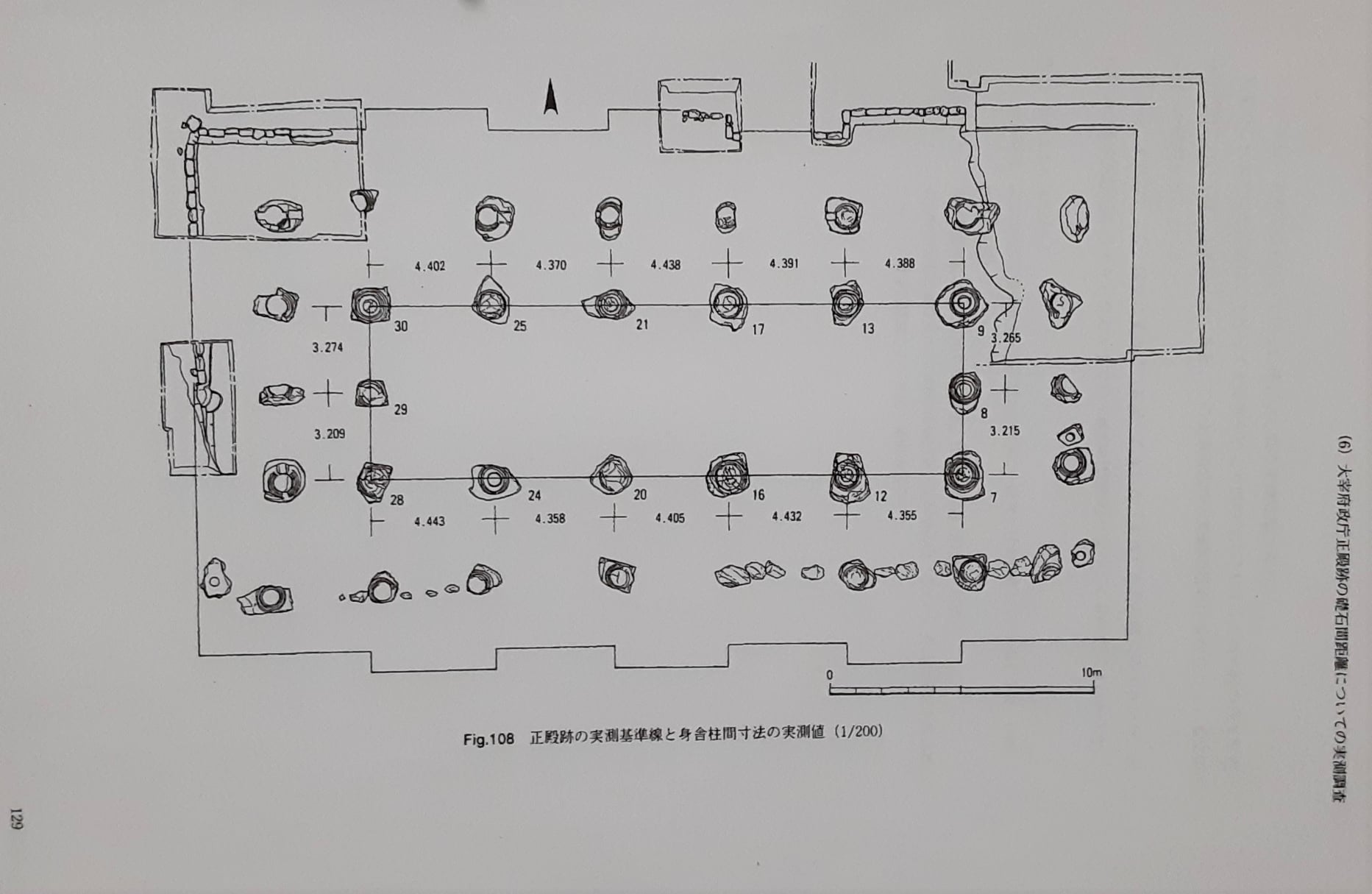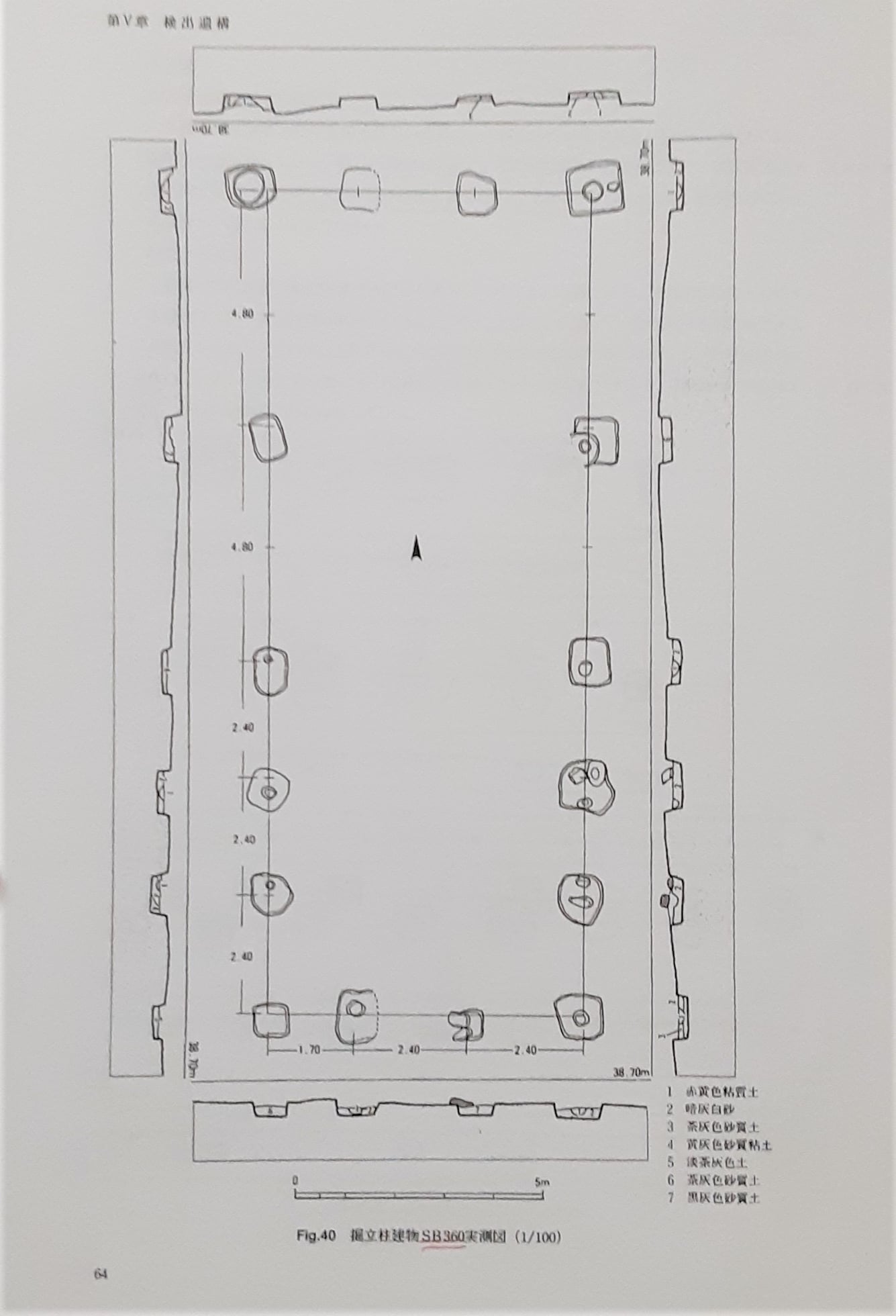太宰府(倭京)の高級官僚、筑紫史益
九州王朝(倭国)による律令官制の成立は、筑後(久留米市)から筑前太宰府(倭京)に遷都した倭京元年(618年)から始まり、順次拡張された条坊都市とともに官僚機構も拡充され、前期難波宮(難波京)や大和朝廷の藤原京へと受け継がれたとする仮説を「洛中洛外日記」(注①)で提起しました。すなわち、太宰府(倭京)こそが「官人登用の真の母体」だったのです。その太宰府高級官僚の一人、筑紫史益(つくしのふひと まさる)について紹介します。
『日本書紀』の持統天皇五年正月条に持統天皇による次の詔が見えます。
「詔して曰わく、直広肆筑紫史益、筑紫大宰府典に拝されしより以来、今に二十九年。清白き忠誠を以て、あえて怠惰まず。是の故に、食封五十戸・ふとぎぬ十五匹・綿二十五屯・布五十端・稲五千束を賜う」『日本書紀』持統天皇五年(691年)正月条
この記事によれば、持統五年(691年)の29年前に筑紫史益が筑紫大宰府典に拝命されていたのですから、662年(白鳳二年)には筑紫に大宰府があり、律令制官職(注②)と思われる大宰府の「典」があったことを示しています。これは大宰府政庁Ⅰ期と条坊都市造営の時代に相当し、当時の九州王朝(倭国)に律令と律令官僚が存在していたことの史料根拠の一つになります。
この筑紫史益についての九州王朝説の視点から論じた論文があります。下関市の前田博司さん(故人)の「九州王朝の落日」という論文(注③)が1984年に発表されています。一部引用します。
【以下、引用】
筑紫史益に与えられていた位階は直広肆でありこれは後の従五位下にあたる。当時筑紫大宰であった河内王は西暦六八六年には浄広肆の位にありこれは後の従五位下にあたる。西暦六九四年に筑紫大宰率に任じられた三野王も同じく浄広肆であり、『日本書紀』天武天皇十四年正月の条に「浄」は諸王以上に与えられる位であり、「直」は諸臣に与えられる位であるとされていることから、王族と諸臣の違いこそあれ筑紫大宰府の長官にも比すべき位階を筑紫史益が有して居ることは注目すべきことと考えられる。筑紫の大宰は次々に替っても、その下にあって、しかも位階では長官と対等のランクにあり、大宰府典として事実上九州の行政の実務に永年携わっている在地の有力な人物の像を思い浮かべていただきたい。(中略)
典の職はのちの養老職員令によれぱ、大宰府には大典二人、少典二人を置く事になっていて、その相当の官位は大典が正七位上、少典が正八位上であり、三十年程へだたった後代に比して、大宰府典の職位がかなり高いのは何故だろうか。
【引用おわり】
前田さんは「古田史学の会」創設時に全国世話人としてご協力いただいた恩人のお一人で、30年ほど前に古田先生と二人で長門国鋳銭司跡を訪問した時、お世話いただいたことがあります。前田さんが1984年の段階で筑紫史益に注目されていたことは驚きです。
わたしは筑紫史益の位階「直広肆」や姓(かばね)「史」の他に「筑紫」という名前にも注目しています。九州王朝の天子が筑紫君磐井や筑紫君薩野馬のように「筑紫」を名のっていることを考えれば、同じく「筑紫」の名を持つ筑紫史益も九州王朝王族の一人ではないでしょうか。そのため、前期難波宮創建の後も高級官僚として太宰府に残ったのではないかと推定しています。なお、701年の王朝交替後も「筑紫公(ちくしのきみ)」を名のる官人の存在を紹介した論文(注④)をわたしは発表しました。引き続き、九州王朝官僚の研究を続けます。
(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」2666話(2022/01/21)〝太宰府(倭京)「官人登用の母体」説〟
②『養老律令』職員令に「大宰府典」が見える。
③前田博司「九州王朝の落日」『市民の古代』6集、市民の古代研究会編、1984年。
http://furutasigaku.jp/jfuruta/simin06/maeda01.html
④古賀達也「九州王朝の末裔たち 『続日本後紀』にいた筑紫の君」『市民の古代』12集、市民の古代研究会編、1990年。
http://furutasigaku.jp/jfuruta/simin12/matuei.html