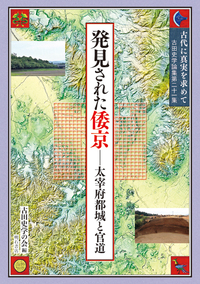福岡市で「邪馬台国」時代のすずり出土(2)
犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員、久留米市)から送られてきた朝日新聞(2月17日)には、「古墳時代 博多で何書いた?」という見出しですずり出土が報じられていました。読者の興味をひくための見出しと思われますが、それであれば本文中に何を書いたのかの解説があってしかるべきです。ところが、古代の博多にあった奴国が文字を使用していたと述べるにとどまる中途半端な記事となっています。
朝日新聞社と言えば古田武彦先生の名著『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』(初期三部作)を発刊し、日本古代史学界や古代史ファンに激震を走らせた会社です。その新聞記事の内容がこのレベルでは、朝日新聞も「地に落ちた」と言わざるを得ず、とても残念です。
『古代史再検証 邪馬台国とは何か』(別冊宝島誌のインタビュー)でも紹介しましたように、古代日本列島において筑前中域(糸島博多湾岸)は、文字文化の先進地域です。『三国志』「魏志倭人伝」には次のように倭国の文字文化をうかがわせる記述が見えます。
「文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ」
「倭王、使によって上表し、詔恩を答謝す」
このように倭国やその中心国の邪馬壹国では「文書」による外交や政治を行っていると明確に記されているのです。福岡市の文化欄担当記者であれば、この程度の知識は持っていてほしいと思うのですが、無理な期待でしょうか。
更に同記事では出土した福岡市を「奴国」としていますが、もしそうであれば「奴国」よりも上位で大国でもある邪馬壹国の地はどこだとするのでしょうか。この「奴国」とされた糸島博多湾岸よりも大量のすずりが出土した弥生時代や古墳時代の遺跡は他にあるのでしょうか。たとえば「邪馬台国」畿内説によれば奈良県の弥生時代の遺跡からもっと多くのすずりが出土し、文字文化の痕跡を示していなければなりませんが、同地の弥生遺跡からすずりの出土はありません。
「古墳時代 博多で何書いた?」という見出しで読者の興味を引くのであれば、こうした「答え」も記事に盛り込み、読者の知識の幅やレベルを高めることができます。そうした真の教養に裏打ちされた記事こそ、「クオリティーペーパー」と呼ばれるに相応しいものと思います。なお、公平を期すために言えば、このニュースを掲載した他の新聞も、その内容は朝日新聞と五十歩百歩です。(つづく)